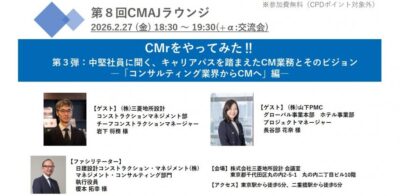概要
大会テーマ:せんのちから
多様性を尊重し繋がりを生み出す、社会と建築のあり方について
The Expertise of 1000
Respecting Diversity and Creating Connections:
Society and Architecture
公益社団法人 日本建築家協会(JIA)は、2025年11月7日(金)、8日(土)の2日間、千葉県文化会館と千葉大学ゐのはな同窓会館を会場に「JIA建築家大会2025千葉」を開催します。今年の大会テーマは「せんのちから」です。
今、私たちの身のまわりにはさまざまな問題が溢れています。〈持続性をもつ好ましい社会〉を実現するためには、幅広い分野にわたる多様な知見や職能、技術の融合が欠かせません。私たちは、これらの課題解決に取り組んでいる建築家、技術者、行政、運営者、市民、学生など計100名以上に登壇していただき、これからの建築や地域について共に考える、1,000人会議を企画しました。20を超えるトークセッションを通して、多様性を尊重し繋がりを生み出す、社会と建築のあり方について考えます。
大会基本情報
| イベント名 | JIA建築家大会 2025 千葉 せんのちから |
|---|---|
| 日時 | 2025年11月7日[金] 10:30-17:30(開場10:00) 2025年11月8日[土] 10:00-17:30(開場 9:30) |
| メイン会場 | 千葉県文化会館 〒260-8661 千葉県千葉市中央区市場町11番2号 ※11/7開催の一部の企画のみ「千葉大学ゐのはな同窓会館」が会場になります。 |
| サテライト会場 | 千葉大学ゐのはな同窓会館 〒260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻1丁目8−1 |
| 交通案内 | メイン会場 千葉県文化会館 ・千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩10分 ・JR「本千葉駅」より徒歩11分 ・京成「千葉中央駅」より徒歩20分 ・バスJR「千葉駅」中央改札(東口)、京成バス7番乗り場より「大学病院」または「南矢作」行き/千葉シティバス6番乗り場「川戸都苑」行きに乗車、「郷土博物館・千葉県文化会館」下車より徒歩2分サテライト会場 千葉大学ゐのはな同窓会館 〒260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻1丁目8−1 ・千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩16分 ・JR「本千葉駅」より徒歩17分 ・京成「千葉中央駅」より徒歩22分 ・バスJR「千葉駅」中央改札(東口)、京成バス7番乗り場より「大学病院」または「南矢作」行き/千葉シティバス6番乗り場「川戸都苑」または「千葉大看護学部入口」行きに乗車、「千葉大看護学部入口」下車より徒歩2分 ※「千葉県文化会館」と「千葉大学ゐのはな同窓会館」は、徒歩7分の距離にあります。イベント当日は、会場間を歩いて移動していただきます。 |
| 参加 |
学生は一般参加にて、事前登録なしで無料で参加できます。一般参加 JIA会員 |
ごあいさつ
 佐藤尚巳
佐藤尚巳公益社団法人
日本建築家協会 会長
変革に立ち向かう「ちから」
明治期の西洋文明の導入とともに建築設計の専門家として建築家が誕生し、社会に貢献する志を共にする者が集い、さまざまな変遷を経て1987年に日本建築家協会が設立されました。持続可能で魅力的で調和した環境の創造と維持のために活動をしています。さて、…
 栗生 明
栗生 明JIA建築家大会2025千葉
大会委員長
あまたの専門家をあつめて
JIA建築家大会は1987年、設立記念大会として東京で開催以来、コロナ禍の2年を除いて毎年、全国で場所を変えて開催してきました。千葉での開催となる本年の大会テーマは、「せんのちから」です。「ひらがな表記」は…
 渡邉太海
渡邉太海大会統括
(JIA関東甲信越支部長)
持続可能な大会のモデルへ向けて
JIAは本部および全国の10支部によって構成されますが、昨年の建築家大会は11月、大分県別府にて開催されました。九州支部の建築家たちの手厚いおもてなしに感動しました。年に一度の大会は、地域の建築家の活動を直に知るとともに会員間の交流にもつながる、…
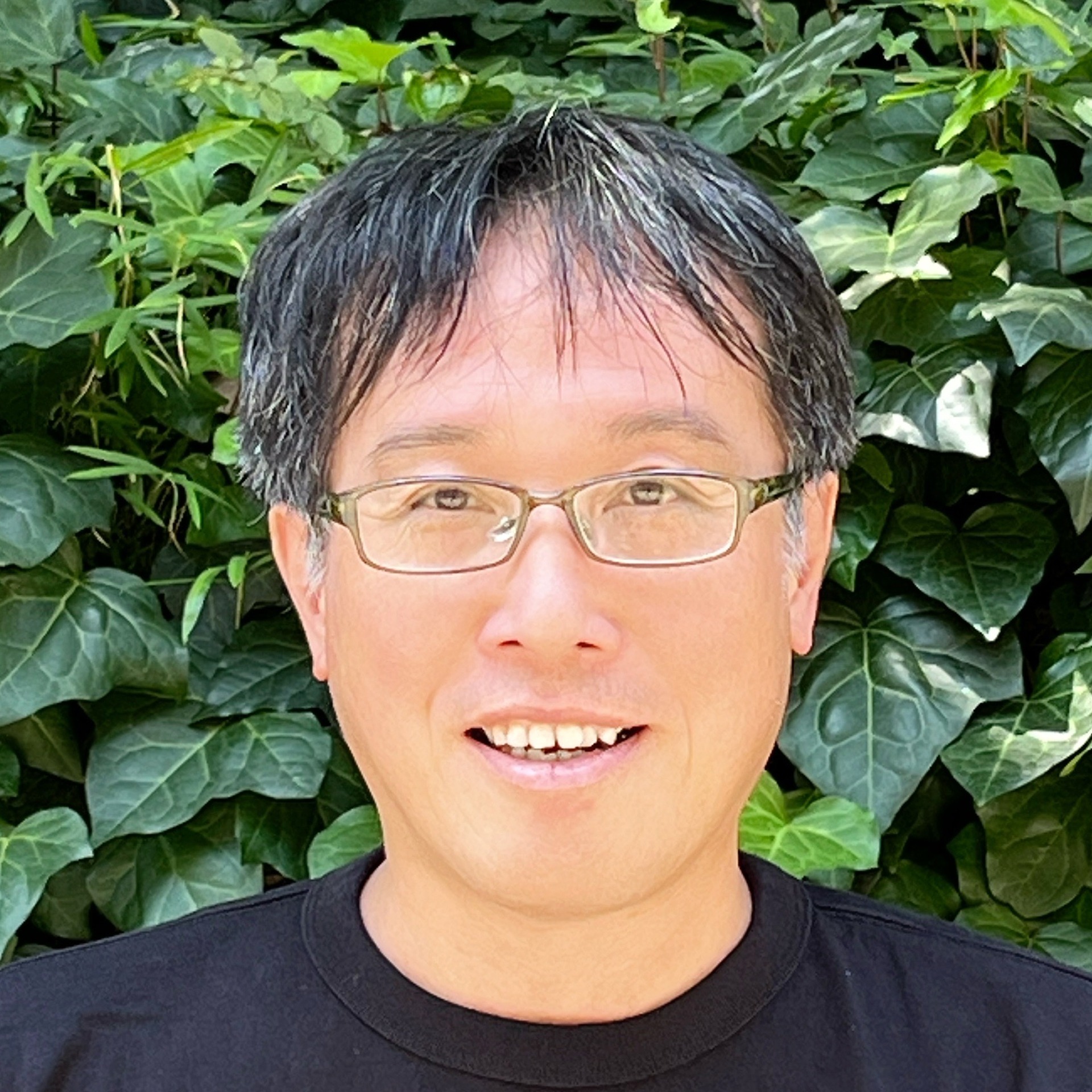 鈴木弘樹
鈴木弘樹大会実行委員長
(JIA関東甲信越副支部長)
みんなが来てよかったと思える大会を目指す
JIA建築家大会2025千葉の日程やプログラムは、例年と趣が違う内容で実施します。持続可能な大会運営が求められるなか、その先駆けとなるよう、みんなが来てよかった、やってよかったと思える、みんなに…
大会プログラム
2025年11月7日[金]|DAY 1
受付:千葉県文化会館
受付開始 9:30 開場 10:00 セッション開始 10:30
*会場の定員を超えた場合、ご入場できない可能性があることをご了承ください。
*なお、会場に変更があった場合などの最新情報は公式サイトをご覧ください。
DAY 1|千葉大学ゐのはな同窓会館(100席)
| ゐのはな同窓会館 |
16:00-17:30
|
|---|
DAY 1|千葉県文化会館大ホール(1,724席)
| 大ホール |
10:30〜12:00
|
|---|
DAY 1|千葉県文化会館小ホール(250席)
| 小ホール |
10:30〜12:00
|
|---|
DAY 1|千葉県文化会館大練習室(100~150席)
| 大練習室 |
14:10〜15:40
|
|---|
DAY 1|千葉県文化会館中練習室(75~100席)
| 中練習室 |
10:30〜12:00
|
|---|
2025年11月8日[土]|DAY 2
受付:千葉県文化会館
受付開始 9:30 開場 9:30 セッション開始10:00
*会場の定員を超えた場合、ご入場できない可能性があることをご了承ください。
*なお、会場に変更があった場合などの最新情報は公式サイトをご覧ください。
DAY 2|千葉県文化会館大ホール(1,724席)
| 大ホール |
10:00〜11:30
|
|---|
DAY 2|千葉県文化会館小ホール(250席)
| 小ホール |
10:00〜11:30
|
|---|
DAY 2|千葉県文化会館大練習室(100~150席)
| 大練習室 |
10:00〜11:30
|
|---|
DAY 2|千葉県文化会館中練習室(75~100席)
| 中練習室 |
10:00〜11:30
|
|---|
EVENTS
ワークショップ
音楽
食
展示
JIAマンス
エクスカーション
主催
公益社団法人 日本建築家協会 関東甲信越支部
https://www.jia-kanto.org/
運営
公益社団法人 日本建築家協会 関東甲信越支部 大会実行委員会
後援
国土交通省|千葉県|千葉市|千葉県教育委員会|千葉市教育委員会|(一社)日本建築学会|(公社)日本建築士会連合会|(一社)日本建築士事務所協会連合会|(一社)日本建設業連合会|(一社)DOCOMOMO Japan|(公社)千葉県建築士事務所協会|(一社)千葉県建築士会|(一社)日本建築学会 関東支部 千葉支所|(一社)日本建築構造技術者協会 関東甲信越支部 JSCA千葉|(一社)千葉県設備設計事務所協会|千葉県森林組合|NHK千葉放送局|BAY FM|千葉県ケーブルテレビ協議会|千葉日報社|読売新聞 千葉支局|毎日新聞社 千葉支局|産経新聞社 千葉総局|㈱日本建設新聞社 千葉総局|㈱日刊建設通信新聞社 関東支社|㈱日刊建設工業新聞社 関東支社